こんにちは、みどり(@hiju39)です。
一ヶ月ほど前に、はじめてクトゥパットを作りました。
クトゥパットはインドネシアのちまきのような伝統料理です。
これまでは買うかもらうかでしたが、今回は時間も意欲もあったので初挑戦!
そのときの様子をまとめたので、楽しく読んでいただけたら嬉しいです。
じゃ~、いってみよう~。
※この記事のYouTube版もあります。
映像や音声で楽しみたい方は、ぜひこちらもどうぞ。
クトゥパットとは?
そもそも、クトゥパットとはなんでしょうか。
・ジャワ島発祥の伝統的な料理
・お米をヤシの葉で編んだ器に入れて、茹でたもの
・日常的に食べられるが、特に断食明け大祭によく食べられる

大まかには上のような特徴があるクトゥパット。なんとなく想像していただけましたか?
クトゥパットと日本の食べ物との類似性
ここで私が「クトゥパットって日本のアレに似ているな」と思った料理が2つありました。
1つ目は「ちまき」。
ちまきって、けっこう地域によって違いがありますよね。私は関西出身なのでちまきというと、細長い円錐形の食べ物で、中は真っ白で甘いおやつです。
でも、「ちまき」でイメージ画像を検索すると、三角形で、中には茶色い具材入りのごはんが包まれているものもあります(関西では「中華ちまき」と呼びます)。
他にもさまざまなバリエーションのあるちまきですが、要は「お米やもち米などを、笹の葉や竹の皮などで包んで蒸した料理」です。
「ゆでる」と「蒸す」で調理法が少し異なりますが、お米やもち米を葉っぱに包んで食べるところがクトゥパットと似ていますよね。
ちなみに、ロンボク島/インドネシアには、ほかにもお米やもち米を葉っぱで包んだ料理やお菓子がたくさんあります。またいつか紹介させてくださいね。
*
もう一つ、似ていると思ったのがお餅です。
お餅も年中いつでも食べられますが、特にお正月にたくさん食べられますよね。クトゥパットも年中食べるけど、「断食明け大祭といえばこれ」という食べもの。年賀状に鏡餅の絵が描かれるように、断食明け大祭のカードにクトゥパットのイラストがあしらわれることも多いんです。
クトゥパットはインドネシアにイスラム教が入ってくる前からあり、その原形は豊穣の神様へのお供えものだったそう。神様への祈願や感謝の印として祝祭の日に食べられるところも似ています。
クトゥパットの器(容れ物)を作る
まずはじめに、クトゥパットの器の部分を作らなければなりません。
が、難しそうなので私はパス(笑)。
ロンボク島に来た当初は「いつかできるようになりたい」と思っていましたが、何度も見ているうちに「手先の不器用な私は、これは他者にお任せしたほうが良さそうだ」と考えを改めました。
というわけで、市場へいきまーす。
普段、クトゥパットの容れ物(インドネシア語では「kulit(皮)」といいます)は市場では売られていません。ですが、今日は売られているのです。なぜなら…レバラン・トゥパット前日だから!
レバラン・トゥパットとは、イスラム教の断食明け大祭(レバラン)の7日後にあたる日のこと。西ジャワ島をはじめとした一部の地域では、この日にクトゥパットを食べてお祝いします。
ロンボク島でも、特にジャワ島に近い西ロンボクや北ロンボクの西部では、断食明け大祭以上に、レバラン・トゥパットにクトゥパットを食べます。
一年で最もクトゥパットが消費される日の前日なので、市場でクトゥパットの容れ物やその材料となるヤシの葉が大量に売られているのです。

クトゥパットの容れ物はさまざまな形や編み方があります。私はオーソドックスな菱形のものを5つ買いました。5つで1万ルピア(約85円)で購入。
容れ物ではなく、クトゥパットそのものを予約注文することもできます。近所の方や親戚などに「作って売ってほしい」と頼めばオッケー。
自分で編んでみたいんです!という方には、残念ながら、この記事はなんの手助けにもなりません。youtube に編み方がでていますので、「cara membuat kulit ketupat」などで検索して下さいね。
市場では、クトゥパット用の「janur(ココナッツの葉っぱの若いもの)」を探しているといえば、売り場を教えてもらえるはずです。ロンボク島では、クトゥパット10個分の葉っぱが10000ルピアで売られていました。※緑色の葉っぱでも編めますがやや硬いので、若い白っぽい葉っぱがおすすめとのこと。


お米を容れ物に詰める
容れ物を手に入れて帰宅。やっとスタートラインに立てました。さあ、いざ手作りです!
まずは、お米の下準備を。お米は洗って、吸水させ、ザルにあけて水をきります。私は15分だけ吸水させましたが、1時間と言っている方もいました(15分でもおいしくできたよ)。
次は、いよいよ容れ物にお米を入れていきます。
が、私は市場で姉たちが器を作っているときにこんな疑問をもちました。
「これ、どこからお米いれるの?」
下の写真ように、二本の長い葉っぱが伸びているところがお米を詰める口になります。

この上↑の写真の赤い丸で囲ったところにある葉っぱをそっと横にずらすと、入口が現れます。

ここへスプーンでお米を入れていきますよ。

お米が濡れているので、なかなかうまい具合には入れられません。
基本こぼれます。
私なんてボロボロこぼしました。こぼれる前提でボウルの上なので作業するといいでしょう。
ペットボトルの飲み口の部分を入口に挿して、小さな漏斗のようにして詰めている人もいました。実は私もやってみたんですけど、お米がペットボトルをうまく滑ってくれなくて、スプーンのほうが早いと思いました。お好きな方法でどうぞ。
あ、そうそう。一つ大事なポイントがあります。
それは、上いっぱいまで詰めないこと。
このあと容れ物ごと茹でるのですが、茹でると米粒が膨らみます。なので、詰めるお米の量は容れ物の半分から2/3あたりまでにして下さいね。私は半分にしました。

茹でて乾かす
ここまできたら、あとは茹でるだけ~。
実は私、今回義姉に尋ねるまで、クトゥパットは蒸して作るのだと思っていたんです。が、尋ねて正解、茹で料理でした。
私は事前に市場で聞いていた義姉の言葉を思い出しました。
「え、茹で方? 簡単だよー!」
「鍋に水を入れるでしょ。で、クトゥパットをいれるの。そのまま火にかけて、沸騰するよね。しばらくしたらクトゥパット(の中の米)が水を吸うから鍋の中の水が減るの。そしたら水をさして。また火にかけて、沸騰させたまま茹でて水を吸わせる。減った分の水を加える。また沸騰させて水を吸わせる。こうやって3回水を吸わせたらできあがりだよ!」
「わかったー!ありがとう。簡単だね」
このとき、私は「ちゃんと茹で方まで聞いた私、偉い」と自分に拍手をしていました。
しかし、家で鍋を目の前にして新たな疑問発生。
「水を吸わせるってどれくらい?」
あかん、全然わからん。イメージができません。なんとなくやればできそうな気もするけど、水量の二センチ分くらい吸わせればいいのか、それとも半分くらい吸わせないといけないのか…。いや、ご飯を炊くのと同じだと考えると、さすがに半分はないか。
なんにせよ、この曖昧さは失敗のもとになりそう。
しかも、何気にけっこう時間かかりそう。
葉に包んでいるとはいえ、そんなに時間かかるの?だって、お米でしょ?
もっと早く作りたいよー。
というわけで、またまたyoutube先生にお世話になることに。
さすがyoutube先生、いい方法を教えてくれました。
流行りの方法なのか知らないけれど、こぞって「30分茹でるだけ!」とタイトルに書いてあったのは次のような茹で方です。
1.沸騰した湯で15分茹でる(蓋をする)
2.蓋をしたまま火を止めて30分放置する
3.1と2をもう1回繰り返す
つまり、「15分茹でて→30分放置し→15分茹でて→30分放置する」の流れです。
まぁたしかに茹で時間は30分だけど…全部で1時間半かかるやん。
30分茹でる「だけ!」はちょっと盛ってません?

茹でるときのポイントは2つ。
・クトゥパットを完全に湯の中に沈ませる(たっぷりの湯を使う)
・茹でるときも放置するときも鍋に蓋はしたままにする
とにもかくにも、中までしっかりと火を通すのだ!という気合いが感じられますね。逆にいえば、中まで火がとおるならどんな茹で方でも良さそうです。
茹で終わったら、クトゥパットを鍋から出します。熱いので注意してね。
そうそう、小豆を茹でたあとのように、茹で汁が赤くなっていることがあります。クトゥパットもほんのり赤くなっているかも。でも、これはそういうものなので気にしなくていいですよ。赤くなるのを避けたい人は、はじめのお米の下準備のときに長めに吸水させて、茹で時間を短くするといいそうです。
さて、風通しのいいところに干して乾かします。
我が家は洗濯竿に吊り下げて干しました。

なんだかクトゥパットも気持ちよさそう~。
ここでしっかり乾かさないと、中のごはんが腐りやすくなります。逆に、すぐに食べるのなら乾かさなくても問題ありません。
うちは翌日のレバラン・トゥパット用に作ったのでしっかり干したのですが、乾いたのを見た瞬間、なんと娘が「早く食べたい」と言い始めました。

「クトゥパット、好きじゃなかったやん?」
「へへへ」
自分で作ると食べたくなるんですよね。
クトゥパットはカレーライスのライスように、ほかのお料理(とくに汁気のある料理)を添えて食べます。断食明け大祭のときなら、ほとんどがオポールアヤム(鶏肉をスパイスで味付けしたココナッツミルクで煮込んだ料理)と一緒に食べます。
まだなんの料理も作ってないので、娘はクトゥパットだけをそのまま食べました。

容れ物から取り出したクトゥパットをそのままもぐもぐ食べるプーちゃん(娘)。
「おいしい?」
「ごはんの味」
「そりゃそうや」
何も味をつけていない、プレーンなごはん味。だからこそ、どんな料理とも合うんです。
翌日のレバラントゥパットでは、断食明け大祭でオポールアヤムを食べ飽きた夫から「もうオポールいらない。麺がいい」とリクエストがありました。
初めてのクトゥパットとインスタントラーメンの組み合わせ。

この記事を書いているときに、ちょうど娘の友達が遊びに来ていました。
記事を覗き込んでいたので、「クトゥパットとミー(麺)を一緒に食べたんだよ」と説明すると、「これこれ!」「おいしいよね!」と口を揃えていました。意外とどこの家庭でもこんなふうに食べているのかもしれませんね。
*
はじめてクトゥパットを手作りしてみた感想は、「工程自体は簡単だけど、時間がかかるぅぅぅ」です。でも「学校やめてよかった」とも思いました。時間がないとなかなかこんなふうにはできないですからね。ハレの日の食文化を一つ経験できたのが嬉しかったです。
娘にも私にも、きっと夫にも? 楽しい思い出つきのおいしいクトゥパットとなりました。
もともと私は食べ物や料理は大好きなので、これを機にいろんなロンボク料理/インドネシア料理を作っていきたいと思いました。
もし、おすすめのインドネシア料理や「これ作ってみてほしい」という料理があったら、ぜひコメント欄やXなどで教えて下さいね。いろいろ挑戦したいです!
以上、今日はここまでです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
今日もお互いサマサマ幸セナン♪
(文責:みどり/Midori Rahma Safitri)
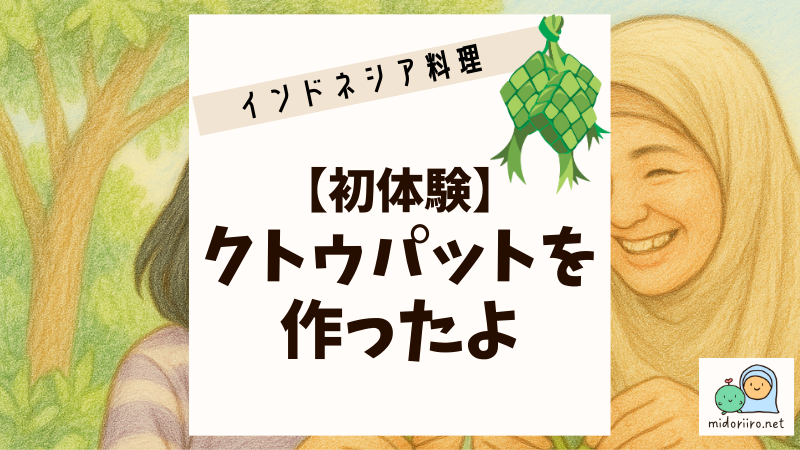
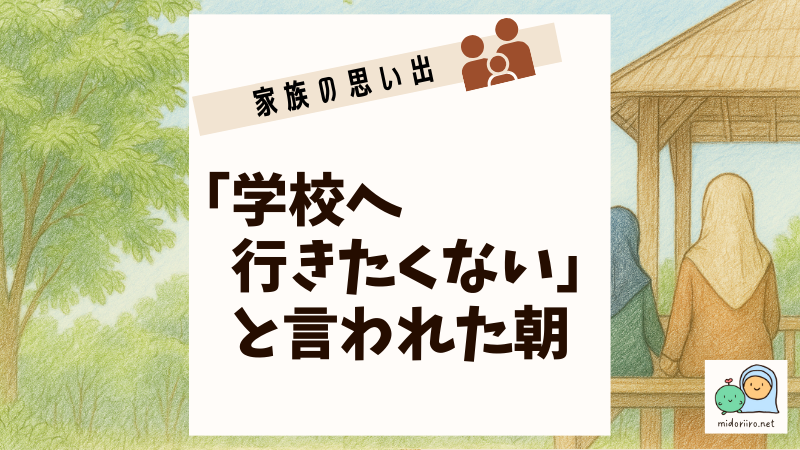

コメント